
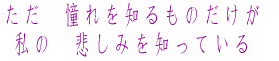

| 雨 音 佐藤 さと 僕は一生 片思いのまま 死んで しまうような 予感がします。 あなたへの 恋も 革命も すべて 片思いのまま 終わって しまうような 気がします。 外は朝からの雨。 とりとめもなく降り続く雨が 僕に一つの甘い思い出を 呼び起こした。 織戸やすこさん。 僕は文芸部の先輩の織戸やすこさんに 一度だけ会ったことがある。 京都のひとだと先輩から聞いていた。 僕が入部した時にはすでに退部していた。 だから僕は その日まで彼女が同人誌に残していった 作品からでしか彼女を知らなかった。 ー実はすべて 女は書くべきなんかではない のではなかろうか。書こうとすればするほど女として 愛されることも 自ら去っていってしまうのではなかろうか。ー 「十一月の水溜り」より 織戸さんがふらりとサークルボックスにやって来たのは 昨年の冬のことだった。 サークルボックスには僕一人しか居なかった。 初めて会った彼女は何よりも落ち着いていて、しとやかな そぶりはまさに手弱女〔たおやめ〕という風だった。 色白、細面、長い睫毛、ひどく目が澄んでいた。 彼女の痩せた身体全体に漂うしっとりとした雰囲気に 僕は大人の匂いを覚えた。 彼女の声は今にも壊れてしまいそうな位、か細かった。 「わたし大学 やめるわ。京都に帰る。 服部さんに伝えてね。」 服部さんとは部長のことだった。織戸さんとは同期だ。 「やはり 女の人には大学は必要ないのかな。」 と僕が話すと 「そうね。やっと わかった。・・・・・」 と 古い同人誌をめくりながら応えてくれた。 僕は彼女の哀しそうな口調に次の言葉を なかなか みいだせなかった。 「・・・・・・・・・・・」 薄暗いサークルボックスの 隅っこで椅子にちょこんと腰掛けて俯いて同人誌を読んでいた 彼女の横顔とその頬紅が美しかった。 「・・・・・・あの・・・僕 以前から織戸さんに 会ってみたいと思っていました。 ・・・・どんな ひとだろうと 想っていました。」 すると 彼女はさして驚いた様子も見せず振り向いた。 「あなたのペンネームは?」 「佐藤 さとです。太宰と北杜夫、好きです。」 「太宰?・・・・・・」 顔を曇らせ、織戸さんはそっぽを向いた。 「じゃ、読まないようにするわ。」 持っていた同人誌を閉じて サークルボックスの壁に貼られた ステッカーを見つめていた。 −子供なんて、大嫌いだわ。− 「散り散りの秋」より サークルボックスを見回して 足元に転がっていた七輪に触れながら言った。 「この七輪、まだ、おいてあったの。・・・・・・。」 「これで、大学祭の時、みんなでオデン屋をして・・・・。」 「楽しかったわ。・・・・一年生の時だった。・・・・。」 まるで、独り言を言っているように話していた。 淋しそうなひとだった。 ー喜びを感じることの少ない自分は、 もっとも不幸な人であるかも 知れなかった。 けれども、もっとも苦しみを味わうことの少ない人が もっとも幸福な人とは知れない。− 「散り散りの秋」より 「ありがと。・・・・。服部さんによろしくと・・・・。もう帰るわ」 「また、来てください。」 彼女は応えることもなく足早にサークルボックスを去っていった。 僕は扉の前で見送った。 思わず後ろをついていきたくなるようなひとだった。 ー彼女は、生きているというより、漂っていた。− 「瞽女〔ごぜ〕」より あの日は果たして雨がふってたのか どうか知らん? 記憶は定かではありません。 けれども今日の雨音を聞いていると、 彼女がひとりで歩いて帰っていった時の 黒いワンピースの後ろ姿と 足音を思いだした。 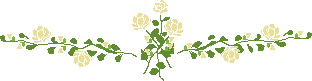 後ろ姿しか見せない あの女〔ひと〕に恋をした 逃げていく女〔ひと〕に 僕は何をしてあげられるのだろう 儚い夢に憧れて 今日まで生きてきたけれど 一度佇ちすくんだ僕には もう彼女が見えず 哀しい浮世のよくある話 僕の夢が夢であるためには 夢は決して実現できない 幻想であることをしらなければならなかった。 とぼとぼと歩く 暗い夜道を通り抜ける秋風に 僕は口付けをし あの女〔ひと〕の残した 髪の匂いを深く吸い込む ころころと転がる秋の枯葉一枚 否、春に堕ちた枯葉一枚 やさしさと弱さを混同している 女々しい男の飲む酒は 甘美な思い出にひとり酔うこと 歌を忘れたカナリアよりは あたしゃ 鳴いて血を吐くホトトギス あの女〔ひと〕は今夜も歌っているだろう うらぶれた 場末で 乾いた唇から血をながしながら 夢 売ります 夢 売ります と 歌っているのだろう 〔20歳〕 |
次頁へ |

